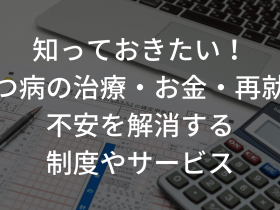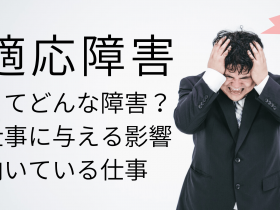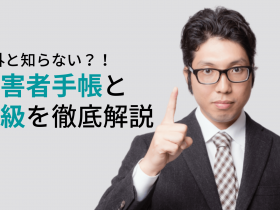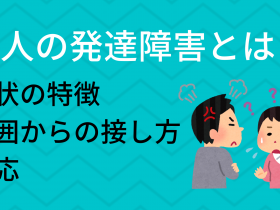うつ病で退職する際の流れ|仕事を辞める前後の対応と支援制度を解説
更新日:2025年07月15日
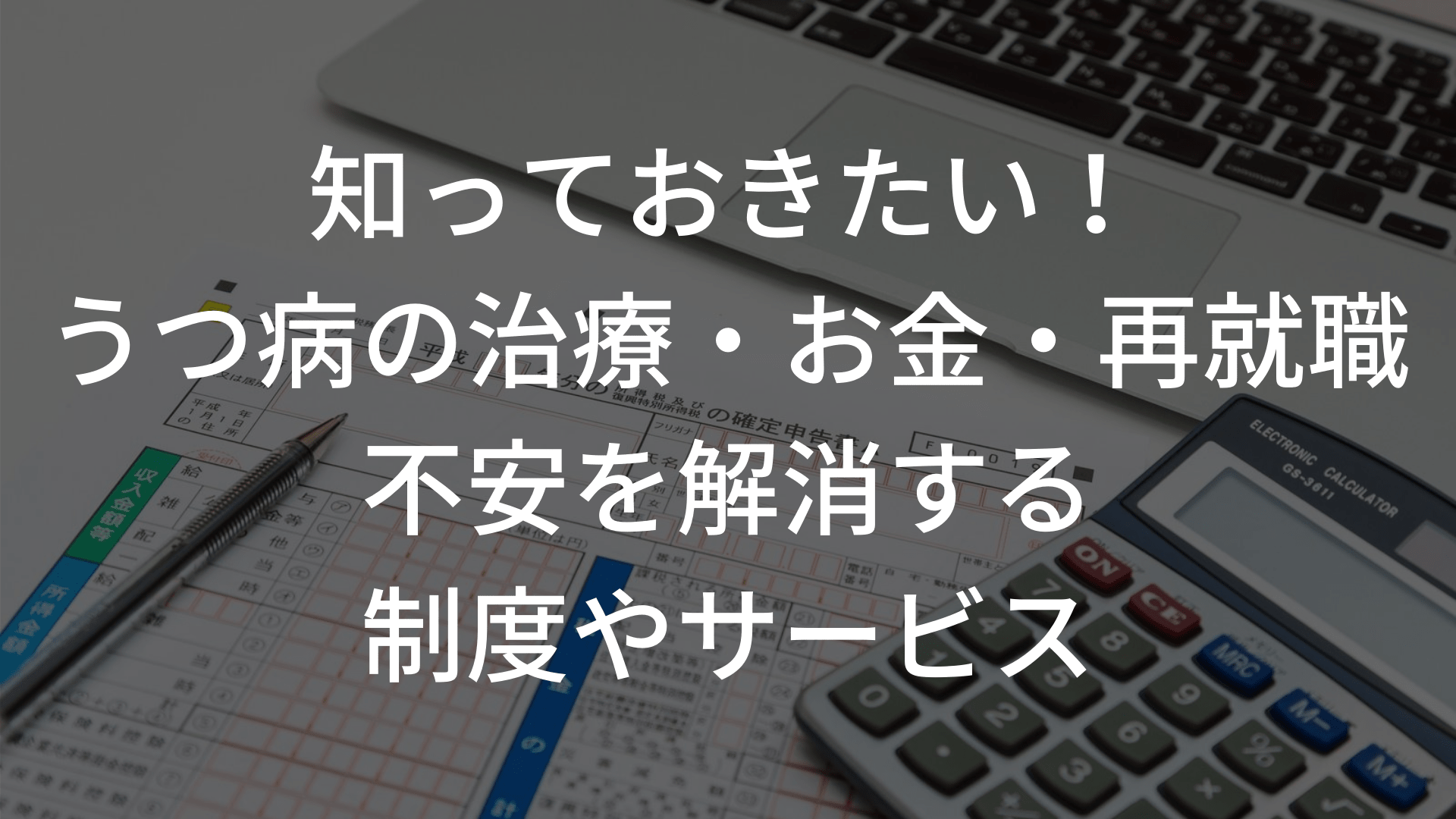
あれほど楽しかった、生きがいだった仕事が楽しくなくなった、職場に行きたくない、やりがいを感じなくなった。思い切って精神科で診てもらったらうつ病と診断された。ただ、一人暮らしで生活しているため、経済的な面や今後の再就職のことなどが不安で仕事は辞めたくない。でも、うつ病の症状で仕事ができる状態ではない…
こうした話は働いていてうつ病を発症した人の多くが直面する問題です。実際のところ、うつ病の症状を抱えたまま仕事を続けても重症化する可能性が高いため、もし退職が可能なら思い切って休むのも一つの手です。ここではうつ病で止むを得ず退職してしまっても、治療、経済面、再就職など退職後の不安が緩和されるように、利用できる様々な制度をご紹介していきます。
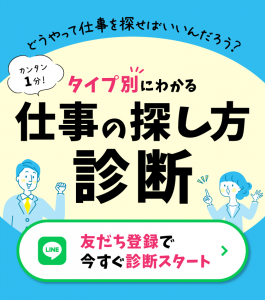
目次
うつ病で退職を決める前にやっておくこと
うつ病は、誰でもなる可能性のある身近な病気です。一生のうちに、約15人に1人がうつ病を経験すると言われています。
しかし、うつ病の症状は人によって異なり、気づきにくい場合が多いです。また、例え気づいたとしても周囲に迷惑をかけたくないという気持ちから、一人で悩みを抱え込んでしまう方も多くいます。
うつ病の治療において、早期発見・早期治療は非常に重要です。特に「しっかり休養を取ること」が第一歩とされています。治療のために退職することは、甘えではなく、治療に集中するための重要な選択肢です。退職を選択肢の一つとして考えることで気持ちが楽になったとという方も少なくありません。
とは言え、退職後に収入の減少や再就職の難しさから後悔することもあるため、慎重に選択をすることが必要です。退職を決める前に以下の5つのポイントを実践してみましょう。
医師に相談する
うつ病で退職を考えている場合、まずは精神科や心療内科などの専門の医療機関を受診し、症状の評価と適切な治療を受けましょう。そのうえで、退職するかどうかを医師に相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。医師は、現在の症状や治療状況を把握し、退職が適切な選択かどうか、または他の選択肢があるかを客観的な視点からアドバイスしてくれます。
家族や支援機関に相談する
うつ病で退職を考えている場合、家族に相談することも非常に重要です。家族の理解と協力は、治療をスムーズに進める上で大きな力になります。家族に相談する際には、まずは自分の状況を正直に伝え、不安な気持ちを共有しましょう。そのうえで、家族の意見も尊重し、一緒に最適な退職後の生活を検討することをおすすめします。
家族への相談に加え、就労移行支援事業所、ハローワーク、地域障害者職業センターなどの支援機関への相談も視野に入れると良いでしょう。これらの機関は、うつ病に関連する就職・転職の相談や就労支援プランの作成、職場定着支援を提供し、労働環境の調整も行ってくれます。支援機関を利用することで、適切なアドバイスや指導が受けられるため、有効に活用しましょう。
異動申請や休職することを検討する
うつ病で退職を検討されている場合、退職前に、部署異動の可能性を会社に相談してみるのが良いでしょう。現在の部署での業務や人間関係がストレスの原因となっている場合、部署異動で改善が見られる可能性があります。部署異動が難しい場合は、業務内容の変更や勤務時間の短縮などで、現在の職場での負担を軽減できる可能性もあります。
また、休職を検討するのも一つの手です。休職制度の活用は、一時的に仕事から離れて療養に専念できるため、回復の可能性を探る上で有効な選択肢となります。
ただし、休職制度は、すべての企業や団体に存在するわけではなく、それぞれの事業者が就業規則に基づいて独自に定めているものです。まずは職場に休職制度があるかどうかを確認し、ある場合は、給与補償の有無や休職期間なども確認しましょう。
労災申請を検討する
職場の長時間残業やハラスメントなどが原因でうつ病になった場合、労災保険を検討しましょう。
労災保険は短時間労働者を含めた全労働者が対象の公的保険制度です。労働者の業務上の事由または通勤による傷病などに対して、必要な保険給付を行います。
労働災害が発生した場合、職場に経緯を説明し所定の書式を記入して労働基準監督署に提出します。労災と認定されれば、労災保険による補償が受けられます。
なお、精神障害の原因が特定しづらく、私生活を含む多くの要因が複雑に影響し合って発生するケースが多いため、うつ病などの精神障害に関しては認定が難しいと言われています。また、うつ病が労災として認められるためには、「発病前のおおむね6か月の間に、仕事上で強い心理的負荷(ストレス)を受けていたこと」が必須の条件となるなど、条件設定が厳しいのは現状です。
しかし、認定されるかどうかは状況次第なので、一人で悩まず、一度、医療機関や弁護士などの専門家に相談してみましょう。
休職・退職後の費用面の確認をする
退職前に経済面を確認することも重要です。うつ病で退職した場合、経済的余裕がないと不安や焦燥感が増し、症状が悪化する可能性があります。また、転職活動が長引く場合も考慮し、貯金を確認することが大切です。
とはいえ、貯金がなければ、退職できないというわけではありません。貯金がない場合は、退職後の生活を安定させるためには、生活費や収入源を確保する計画的な準備が不可欠です。
退職金の支給や支援制度、労働災害に伴う給付、休職中の傷病手当金など、様々なお金の不安を解消する制度があります。職場の制度によって異なるため、ぜひ一度職場に確認してみてください。
うつ病発症から退職までの流れ
診断書を受け取る
・うつ病を発症したらまずは医療機関へ診断書を依頼する
・診断書の提出は必須ではないが、企業によっては診断書の提出を求められることがあったり、場合によっては診断書があることで企業側からの理解が得られやすく、スムーズに退職手続きが進む可能性がある
退職の意思を会社に伝える
・正社員などで契約期間が定められていない場合「退職希望日の2週間前まで」に申し出をすることで法律上は辞めることが可能
ただし、就業規則などで退職に関する独自の手続きが設けられている企業もあるため、雇用契約書などに書かれた退職に関する規定や就業規則などを確認してから、退職手続きを進めるとよい
退職
・退職時にハローワークが発行する「雇用保険被保険者離職票」は、基本的には会社から自宅に送付される
・離職票は雇用保険の申請時に必要となる書類のため、事前に会社へどのくらいで手元に届くか確認しておくと安心
各種保険の切り替え手続き
・厚生年金および健康保険組合(もしくは協会けんぽ、共済組合など)に加入していた場合、厚生年金は国民年金へ、健康保険は国民健康保険などに切り替えの手続きを行う
・退職後に配偶者などの被扶養者となる場合は被扶養者になるための手続きが必要
退職後のうつ病の治療を継続するには
退職には色々な決断や不安が伴いますが、うつ病などの傷病が理由で仕事を継続できない場合、病気の治療に専念することは重要です。うつ病は仕事を続けながら、つまりストレスを抱えたまま、または短期間で治すことは難しい病気ですし、基本的には雇用者(会社側)は被雇用者の意思を尊重しなければなりません。
退職後はまず、治療に専念することが重要です。様々な不安から再就職への行動を起こしたくなってしまいますが、完治とまでいかなくても、寛解するまでは家で休養しつつ、通院、服薬など適切な治療を受けましょう。また、復職までのアクションを進める際には主治医と相談しながら決めていきましょう。
全ての傷病についても言えることですが、決して「軽くなった、治った」と自分で判断せず、通院や、服薬、普段の生活についてもなるべく主治医の指示を守ることが完治への近道です。
退職して治療を続けていく際に不安なのは、療養生活に必要なお金です。次はうつ病での療養生活に利用できる経済的な支援制度を見てみましょう。
退職後のお金の不安を解消する制度
【自立支援給付による精神通院医療】
2013年から施行されている、障害者総合支援法の自立支援給付という制度は、通院による精神医療を継続的に要する病状を持つ人に対して自立支援医療費を支給する制度です。これは、日本の障害者福祉施策の中に位置づけられています。
この給付を受けるには市町村の福祉関係窓口で申請書をもらい、記入・提出します。その際、医者の診断書や障害年金の受給証明書などが必要となります。
具体的な給付内容は、原則としてその疾患にかかる通院での精神医療の月額の9割が公費負担となり、対象者は1割負担となります。その1割負担が高額になる場合は世帯単位の所得により対象者の負担額には上限がつくので、安心して通院治療を受けることができます。
【傷病手当金】
傷病手当金は、正式には健康保険傷病手当といいます。同一の傷病が原因で連続して休職期間が3日以上ある場合、4日目以降の休みについて傷病手当金が支払われる、健康保険における制度です。休職を初めてからの3日間は待機期間と呼ばれ、その3日には公休日や有給休暇日が含まれていてもかまいません。
仕事を休職する際には覚えておきたい制度ですが、退職後も同じ傷病が理由で療養を続け、仕事に就けない場合、最長で1年6カ月、傷病手当金を受給することができます。その際に支給される額は休業前までの1年間の平均月給額の2/3となります。今までの月給の2/3が支給されるのは働いていないことや、治療にどれだけの期間が費やされるのかわからないことを考えると、これまで同様の出費はできないにせよ、あるのとないのとでは大きな違いと言えます。
【障害年金】
障害年金とは、国民年金に加入している場合は障害基礎年金、厚生年金に加入している場合、障害厚生年金と呼ばれます。それぞれ受給条件を満たすことによって支給される年金です。
支給金額については、国民年金加入者は障害の程度(その傷病が日常生活にどれくらい影響を与えるか)によって変わります。1級は年額約97万円、2級は年額約78万円となっており、子どもがいる場合は加算があります。
障害厚生年金については障害の程度により1級から3級までの等級があり、定められた平均標準報酬月額と厚生年金の加入期間によって算出されますので一律ではありません。配偶者がいる場合、要件を満たせば加算があります。
また、厚生年金加入者は国民年金の第2号被保険者でもありますので、障害厚生年金の1、2級に該当する場合は要件を満たせば障害厚生年金と同時に障害基礎年金を合わせて受給できることになります。
事業所で就業している場合、厚生年金保険料は給与から天引きされているので納入漏れがありません。障害の程度は判定次第ですが、一定期間以上働いていれば受給要件は自然と満たせるので安心です。年金制度は国民のための社会保障制度です。ためらわずに市町村の年金窓口に相談しましょう。
【失業保険】
失業保険は、離職後、就職する意思と能力があることが前提に90~360日間支給される雇用保険制度です。支給期間は、傷病、妊娠、出産、育児などの事情がある場合には最長3年まで延長可能です。
退職した職場から発行された雇用保険被保険者離職票をハローワークに提出すると、申請し失業保険の受給の可否、支給額の決定がなされます。基本手当日額は離職前の給与を計算式に当てはめた額の50~80%が一般的です。
この際、離職理由や雇用保険の被保険者であった期間が勘案されます。離職理由が”自己都合による退職”なのか、”特定理由離職”なのかは重要です。傷病などでやむを得ず退職した場合は”特定理由離職者”となります。
特定理由離職者は離職する前の1年間のうち6カ月以上の被保険者期間があれば失業保険給付の対象となります。自己都合による退職の場合は2年間で12カ月以上の被保険者期間が必要です。
うつ病で退職した場合、就職する意思はあっても能力があるのかということが問題となります。これについてはハローワークでしっかり相談しましょう。傷病が理由ですぐに就職できない場合、求職の申し込みはできますが、失業保険の基本手当の対象とならず、求職申込日から15日以上傷病で就職できない場合、雇用保険の「傷病手当金」の対象になり得ます。これは、前述した健康保険の傷病手当とは全く別のもので、同時に両方を受給することはできません。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる
うつ病で退職後に再就職を目指すためには

病院等によるリワーク支援
リワーク支援は正式には職場復帰支援といいます。従来、厚生労働省は事業主が主体となってうつ病などの精神疾患を持つ被雇用者の職場復帰支援することを推進していました。近年では障害者職業センターや、精神保健福祉センターなどの機関や民間の精神科病院などで治療の一環としてプログラムを実施することも可能になりました。
中小企業など、小さい事業所では職場復帰支援の体制が組織されていないので、このような公的機関のプログラムを利用したり、リワークプログラムのある就労移行支援事業所を探したり、通院している精神科や心療内科で職場復帰支援のプログラムの有無をたずねてみましょう。
支援の概要としては以下の通りです。
1.生活リズムの立て直し
2.コミュニケーションスキルの習得
3.職場ストレスへの対処法の獲得を目的とするプログラム
このプログラムは、言い換えれば、社会復帰のリハビリプログラムです。通院治療を継続しながら、復職へ向けての次の段階として、主治医のアドバイスを受け、うつ病の症状が安定したり、軽快してきたらぜひ取り組んでみましょう。
就労継続支援事業所
就労継続支援事業所は障害者総合支援法の自立支援給付のサービスとして就労継続支援をおこなっている事業所です。社会福祉施設という位置付けで、多くは社会福祉法人が運営しています。一般の事業所での就労が困難な障害者に就労の機会、生産活動の機会、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練などを提供しています。
就労継続支援事業所にはA型とB型があります。A型では雇用契約が発生し、最低賃金が保障されますが、B型では雇用契約はなく、労働の訓練という面でもA型よりもゆるやかな運営がされています。どちらも一般事業所からの軽作業や清掃作業の委託、施設独自の作業として農作業、木工や陶芸作品の制作、製パン、製菓及びその販売などを事業とする場合が多いようです。
どちらも作業に対して工賃が支払われますが、B型では雇用契約がないので、工賃もお小遣い程度となります。一方で利用期間に縛りがなく、何年も利用している方もいらっしゃいます。
就労移行支援事業所
就労移行支援事業所も、就労継続支援事業所と同様に障害者総合支援法の自立支援給付のサービスの一つです。就労継続支援事業所と名称が似ていますが、就労移行支援事業所の対象者は一般の事業所での就労を目指す障害者となります。
就労移行支援事業所は、一般の事業所への就労へ移行する訓練をするサービスです。そのため、就労移行支援事業所では一般事業所で働くために必要なスキルを学んだり、個別の就労適性のアセスメント、一般事業所での実習、職場の開拓、就職後のフォローアップなどが実施されます。就労継続支援事業所のような作業はしないため、工賃は発生しません。
就労移行支援事業所の利用者は就労継続支援事業所の利用者よりも障害の程度が軽かったり、就労への意識が高いなど、より一般就労に近いところにいると言えるでしょう。利用期間は原則2年となっています。
いずれの事業も自立支援給付の対象です。利用を希望する場合には障害程度区分の認定を受ける必要があり、その結果によっては希望するサービスが利用できない場合もあります。原則、利用料の9割が公費負担での給付となり、残り1割(所得による上限付き)が自己負担となります。
→うつ症状専門のトレーニングが受けられる障害者専門の就労移行支援サービスatGPジョブトレを見てみる
知って安心、様々な社会保障・社会福祉制度
今回ご紹介した制度やサービスは、今まで大きな傷病もなく健康に生活し、就労していた方には知らないものが多かったのではないでしょうか。うつ病という精神疾患(障害)になるまでは言わば、このような社会保障や社会福祉制度を意識することなく普通に生活できていたからです。知っていたとしても失業保険ぐらいで、それについてもどこにどのように申請するのか、転職・失業した経験がなければ詳細は分からない方もいると思われます。
日本の社会保障や社会福祉制度は「知らなければ損をする」ことが多いのです。また手続きも面倒だったりします。
今回ご紹介した制度をうまく利用すれば、働いていた時の収入よりも減りますが、離職後のうつ病の治療、その治療費や生活費の維持、再就職の道筋も見えることでしょう。退職することの不安も緩和され、症状に苦しみながら無理して働かなくてもよくなります。むしろ、制度を利用しながらしっかりとうつ病と向き合い、完治させて再就職に臨むという選択も安心してできるのではないでしょうか。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
→【LINEおともだち追加】で診断してみる
atGPとは
atGPとは、株式会社ゼネラルパートナーズが運営する各種障害者就職および転職支援サービスの総合ブランドです。
20年以上障害者の就職や転職の支援を行ってきた日本の障害者雇用のパイオニアともいえる存在が、このatGPです。
atGPが提供する就職や転職に関するサービスは、基本的に無料で受けることができます。
障害や難病を抱える人の将来のビジョンや金銭的な課題も含めて、ひとりひとり異なる不安や悩みに関して専属のエージェントが二人三脚で寄り添い、サポートを行ってくれるというものです。
うつ病で生活や就労に関する困りごとを抱えている場合には、atGPに相談することを念頭に置いておくことをおすすめします。