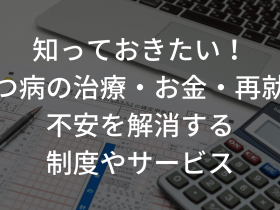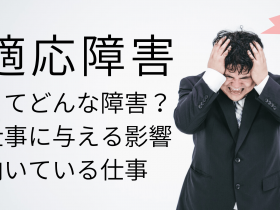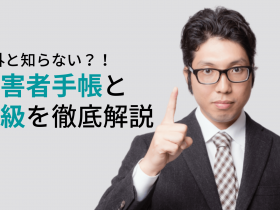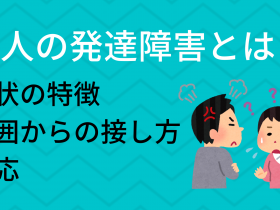段取りができないのは病気?原因と対策について
更新日:2025年11月14日

「段取り」とは、事を運ぶ順番や仕方のことを指します。「段取り八分、仕事二分」という言葉がある通り、仕事において段取り(事前の準備)がとても重要で、仕事の出来の大部分は事前の段取りにかかっています。しかし、世の中には段取りができない人も少なくありません。段取りができない人にはどのような特徴や理由があるのでしょうか。
目次
段取りできない理由
段取りができない人には、次のような特徴があります。
優先順位が決められない
段取りができない人の多くは、優先順位を決めるのが苦手な傾向にあります。効率良く仕事を進めるためには、タスク(作業)の優先順位を決めておくことが重要です。
優先順位が決められない人は、全体のスケジュールや仕事の優先度を考えずに、簡単な仕事や目の前にある仕事から手をつけがちです。その結果として、優先度が高い重要な仕事を後回しにして、本来終わらせなければならない時間に仕事が終わらないことが多いようです。
仕事の全体像や重要性を理解していない
仕事の全体像を理解した上で、タスクを整理しないと優先順位が決められません。全体像を理解することで、初めて優先すべきタスクが見えてきます。段取りができない人は、仕事の全体像を把握しておらず、重要性を理解していないケースが多いようです。
時間を浪費しがち
段取りができない人は、時間を浪費しがちです。段取りができていないと、整理整頓不足による非効率な作業、タスクの抜けや漏れ、作業のミスなどが起こります。
段取りは、仕事に限らず物事を効率良く進めるために必要な準備です。つまり段取りが不十分な状態では、物事を効率的に進めることができないため、多くの無駄な時間が発生します。
自身の能力を考えずすべて自分でやろうと思っている
自分は段取りが苦手と思っている人は、まず自分の能力について理解しましょう。自分だけが頑張っても、うまくいかないことがあります。
例えば、ある仕事を引き受けても、自分ならどの位の時間をかければできるのかを把握できていなければ、時間がかかり過ぎたり、キャパシティーオーバーで他の仕事に手を手をつけられないといった失敗をすることが考えられます。
特に、責任感が強い人や他の人に頼むことが苦手な人は注意が必要です。一人で抱え込まずに、必要であれば他の人に頼むことも大切です。
段取りできないことに関連する病気
病気や障害が原因で、上手く段取りができない可能性もあります。段取りができないことに関連する病気や障害には次のようなものが考えられます。
遂行(実行)機能障害の可能性
「遂行(実行)機能障害」は、物事を論理的に考え、そのプロセスを計画し、効率的に実行することが困難になる障害で、高次脳機能障害のひとつです。
高次脳機能障害とは、脳梗塞やくも膜下出血などの脳血管障害や、事故などによる脳の外傷、心肺停止による低酸素脳症などで脳がダメージを受けたことが原因で、注意力や記憶力、言語、感情のコントロールなどがうまくできなくなる認知機能の障害です。
遂行(実行)機能障害は、言語、記憶、行動に問題が見られませんが、自分自身で物事の優先順位が付けられなくなって、効果的な判断ができなくなるのが特徴です。
遂行(実行)機能障害の症状
「遂行(実行)機能障害」の主な症状には次のようなものがあります。
● 目標を立てることができない
遂行(実行)機能障害の症状として、目標設定に関する障害があげられます。何をしたらどうなるのかイメージがわかず、目標を定めることができないため、計画性がない衝動的な行動をしてしまいます。
周囲からは、無気力で自発性がないと思われることもありますが、実際には目標を立てて達成するために考えるのが困難になっているのです。
● 自発的に行動ができない
目標を立てることができない、または目標をたててもプロセスが計画できないので、自分自身で行動を開始することができません。周囲からは、物事に無関心で自発性が欠けているように見えてしまう可能性があります。
● 受動的になる
言語、記憶、行動には問題がないため、誰かに指示をされると行動することができます。ただし、指示が無ければどうしていいのか分からずに行動できなくなります。例えば、日常生活でも、作業の順序をメモして、その通りでないと行動を始めることができません。
● 自分を客観的に見られない
自分を客観的に見ることができなくなるので、その場の状況の変化に応じて対応することが難しくなります。第三者からの目線で自分の行動を評価することや分析、改善ができないため、同じような失敗を繰り返します。
● マルチタスクができない
遂行(実行)機能障害の大きな特徴の1つとして、同時に2つ以上の作業ができなくなります。優先順位もつけることができないため、2つ以上のことを一度に頼まれると行動に移せなくなります。
注意欠如・多動症(ADHD)の可能性
「注意欠如・多動症(ADHD)」は、不注意や多動性、衝動性などの特性を持つ発達障害です。 「注意欠如・多動症(ADHD)」などの発達障害は、生まれつき脳の性質や働き方、発達の仕方に偏りがあることで生じると言われていますが、その原因についてははっきりわかっていません。
多動性や衝動性が強いタイプは、子どもの頃から「落ち着きがない」「言うことを聞かない」といった特性がみられ、小児科や精神科を受診して診断されることがあります。一方で、不注意の特徴が中心の方は大人になってから気づかれるケースも少なくありません。
注意欠如・多動症(ADHD)の症状
「注意欠如・多動症(ADHD)」は、特性の現れ方によって「多動・衝動性が優勢なタイプ」「不注意が優勢なタイプ」「多動・衝動性と不注意が混在しているタイプ」の大きく3つに分けられます。それぞれの主な症状は次の通りです。
● 多動性
・手足をそわそわと動かしたり、貧乏ゆすりをする
・じっと座っていられない
・気が散りやすく、集中力が続かない
● 衝動性
・思ったことをすぐに口にしてしまったり、相手が話の途中であるのに割り込んで話を始めてしまう
・せっかちで順番を待つことができない
・良く考えずに思いつきで行動してしまう
・自分の思い通りにならなかったり、欲求が満たされなかったりするとすぐにイライラする
● 不注意
・うっかりしてミスが多い
・重要な用事でも期限が守れない
・物事を順序立てて考えたり、やり遂げることができない
・忘れ物や失くし物が多い
・整理整頓ができない
「多動・衝動性と不注意が混在しているタイプ」は、「多動・衝動性が優勢なタイプ」「不注意が優勢なタイプ」の両方の症状が現れるタイプで、「注意欠如・多動症(ADHD)」の方の多くがこのタイプですが、症状の出方は人によって異なります。
段取りできないことで困ること
段取りができないと、仕事や日常生活で困ることがあります。
人間関係の構築が困難になる
仕事においても日常生活においても、ほとんどの場合は周囲の人と連携して物事を進めます。その中に一人でも段取りができない人がいると、物事がスムーズに進まなくなります。その結果として、人間関係に悪い影響を与えてしまうことになりかねません。
優先順位が決められない、手順を度々間違える、作業にとても時間がかかるなど、段取りができないことでの失敗が続けば、周りの人たちからの信頼を失うことになりかねません。自分にはそんなつもりが無くても、他の人の足を引っ張ってしまって反感を買ってしまうこともあります。
職場や学校、普段の生活の中でも、周りの人と良い関係を築いて協力して物事を進めるには、段取りが重要です。
ケアレスミスの多さから時間を浪費する
しっかりと段取りせずに物事を進めると、ケアレスミスをしてしまう可能性が高くなります。たとえ小さなミスでも、ミスがあればやり直す時間がかかります。
ケアレスミスが多ければ、多くの時間を浪費することになりますが、チームやグループで作業を進めているような場合では、自分の時間だけでなく、周囲の人の時間も無駄にしてしまうことになります。
失敗やミスは誰にでもあることですが、できるだけしないようにするには、事前に十分に段取りを考えてから行動に移すことが重要です。
段取りできるようになるには?
これまで解説してきた通り、仕事においては段取りがとても重要です。段取りができない人は、次のことを意識してみましょう。
作業全体を把握して優先度を決める
適切な段取りをするには、タスクの優先順位を決めることが重要です。優先順位を決めるには、作業の全体像を把握する必要があります。全体を把握することで、初めてどのタスクが重要で優先度が高いか決めることができます。
作業量を把握する
作業の全体像を把握すると同時に、作業量とそれにかかる時間も把握しましょう。自分一人で、時間が間に合わない場合は、周囲の人に手伝ってもらうか、計画を見直しましょう。
目的を理解する
段取りで最も重要なことは目的を理解することです。いくら段取りを考えても、目的や目標が間違っていれば、物事を上手く進めることはできません。
段取りをしても、途中で状況が変わって臨機応変に対応しなければならないこともあります。そのようなケースでも目的を理解していれば、改めて段取りを組みなおすことができます。
遂行(実行)機能障害の場合
「遂行(実行)機能障害」では、解決方法や計画の立て方を一緒に考える訓練やマニュアルを利用して段階的に自律して作業を遂行できるよう支援する訓練といったリハビリテーションが行われます。具体的な訓練としては次のようなものがあります。
・ワークブックやトランプなどを活用した机上での作業
・パズルや積み木を組み立てるなどの作業
・家事や予定管理など日常生活動作
・書類作成などの職業的な課題
・数人で作品を制作するグループ課題
・スケジュール管理など社会生活的な課題
注意欠如・多動症(ADHD)の場合
「注意欠如・多動症(ADHD)」の方が、段取り良く物事を進めるには、次の点に注意しましょう。
● マルチタスクをやめる
「注意欠如・多動症(ADHD)」はマルチタスクが苦手です。大きな作業は小さなタスクに細分化して、複数のタスクをやろうとせず一つのタスクに集中しましょう。
● 情報を見える化する
タスクを細分化したら、ToDOリストやチェックリストを作って、やるべきことを見える化します。さらに、スケジュールを立てて進行具合を確認しながら進めましょう。
● 余裕を持ったスケジュールを立てる
余裕を持ったスケジュールを立てると、予期せず事態やトラブルにも対応しやすくなります。多動性で気が散りやすく集中力が続かない人は、タイマーなどを使って集中できる時間を区切り定期的に休憩を挟みます。
注意欠如・多動症(ADHD)で就職転職に不安な方は
段取りができない理由には、「注意欠如・多動症(ADHD)」の可能性もあります。「注意欠如・多動症(ADHD)」の特性によって、就職や転職に対して不安を感じている方は、就労移行支援サービスを利用して、就労に向けたトレーニングやサポートを受けるのがおすすめです。
「atGP(アットジーピー)ジョブトレ」は、障害者の転職サービス業界 No.1の「atGP」が運営する就労移行支援サービスです。うつ病・発達障害・統合失調症・聴覚障害・難病といった5つの障害に特化したコース制なので、就職後も自身の障害とうまく付き合いながら「働き続ける」ためのスキルが身につきます。
まとめ
段取りができない人の中には、「遂行(実行)機能障害」や「注意欠如・多動症(ADHD)」といった病気や障害が原因となっている可能性があります。段取りができなくて仕事や日常生活において、人間関係の構築や時間の浪費などの困りごとを抱えている方は、一度専門の医療機関に相談してみましょう。