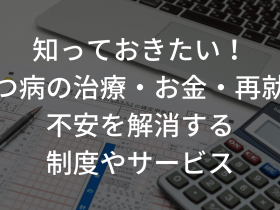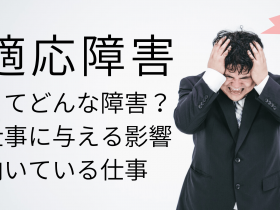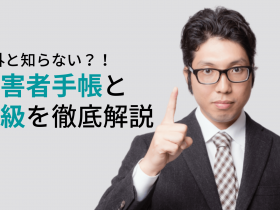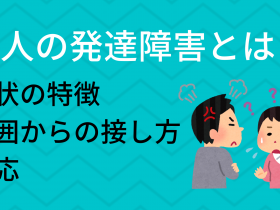物事を深く考えられないのは病気?改善方法などを解説
更新日:2025年11月07日
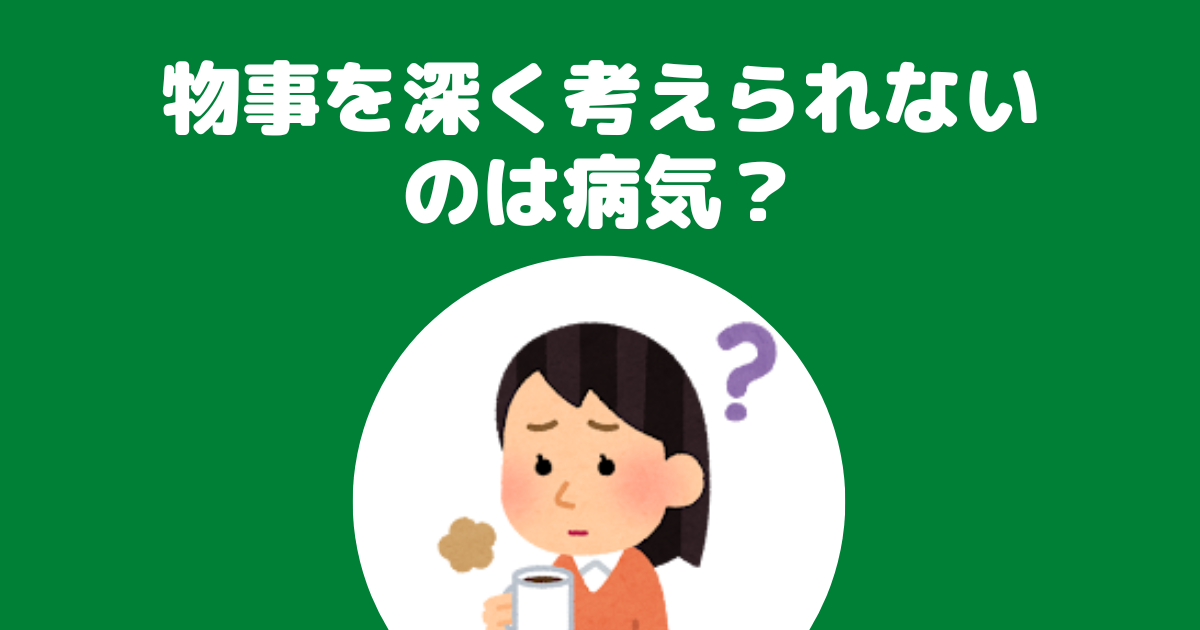
物事を深く考えられないのは、病気のサインかもしれません。病気になると思考力の低下や集中力の低下、考えがまとまらないといった症状が現れることがあります。本記事では、物事を深く考えられないことと関係する病気や、それらの病気になる原因、症状を改善する方法などを解説します。
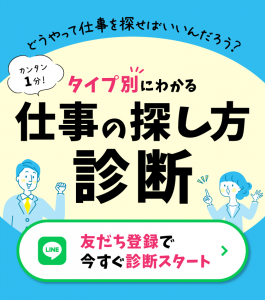
目次
物事を深く考えられないことと関連する病気
疲労やストレス、睡眠不足、栄養不足、運動不足、加齢などさまざまな原因で思考力が低下する事があります。思考力が低下すると物事を深く考えられなくなります。また、思考力の低下は、次のような病気が原因の可能性もあります。
統合失調症
「統合失調症」は、考えや感情、行動がまとまりづらくなってしまう精神疾患です。原因は、まだ完全に解明されていませんが、脳の神経伝達物質の異常、遺伝的要因、環境要因などが複合的に関係しているとされています。「統合失調症」の患者は、日本で約80万人もいると言われていて、決して特別な病気ではありません。
「統合失調症」の症状は、「陽性症状」と「陰性症状」に分類されます。それぞれの症状には次のようなものが見られます。
●陽性症状
幻覚・妄想・思考障害・自我障害・記憶障害
●陰性症状
意欲の低下・感情や感覚の鈍麻・うつ状態・社会的引きこもり
「統合失調症」の方の思考は、まとまりが無くばらばらで、会話はしばしばつじつまが合わなくなります。さまざまな考えが制御されず浮かんできたり、思考が突然中断することもみられます。
適応障害
「適応障害」は、特定のストレスが要因となって、精神面・身体面にさまざまな不具合が起きる疾患です。「適応障害」は、ストレスの元となっている状況や出来事がはっきりしているので、ストレスの要因から離れると症状は次第に改善に向かいます。しかし、ストレスの要因から離れられない場合や取り除けない状況では、症状が慢性化することがあります。
「適応障害」の症状には、大きく分けて精神的な症状、身体的な症状、行動面の症状があります。精神的な症状としては、抑うつ気分、不安、焦り、イライラ感などです。身体的な症状としては、不眠、食欲不振、疲労感、頭痛、動悸、めまいなどが見られます。行動面の症状としては、遅刻や欠勤、ミスが増える、飲酒量が増えるなどが挙げられます。また、これらの症状によって思考力が低下することがあります。
不安障害
「不安障害」は、過度な不安や心配に襲われて、心身にさまざまな不調が現れる病気です。「不安障害」には、社交不安障害・全般性不安障害・強迫性障害・パニック障害などの種類がありますが、不安によって物事を深く考えられなくなることがあります。
●社交不安障害
人前で何かをすることに対して、必要以上の緊張や強い不安を感じて、手が震えたり、汗が出るなどの症状が現れます。不安感が強い場合は、動悸や吐き気、腹痛などの身体症状もみられます。
●全般性不安障害
家族・友達・仕事・学業など日常生活のいろいろなことが気になって、不安や心配な状態が半年以上続きます。不安な気持ちだけでなく、疲れやすい、集中できない、イライラする、眠れないといった症状もみられます。
●強迫性障害
「手を繰り返し洗い続ける」「火を消したか、執拗に確認する」「ドアのカギを何度も確認する」など、不合理と知りながらも一連の行動がやめられず、繰り返し同じことをしていないと不安でたまらなくなります。
●パニック障害
「パニック障害」は、突然理由もなく激しい不安や恐怖に襲われ、動悸・めまい・息切れ・吐き気などの身体症状(パニック発作)により日常生活に支障をきたす病気です。場合によっては、死んでしまうのではないかという強い恐怖を覚えることもあります。
睡眠障害
「睡眠障害」は、睡眠に何らかの問題がある状態のことで、大きくわけて「不眠症」「過眠症」「睡眠時随伴症」があります。「睡眠障害」になると、思考力や集中力の低下、記憶力の低下など、さまざまな認知機能や精神状態に影響を与える可能性があります。
●不眠症
「不眠症」は、入眠困難・中途覚醒・早朝覚醒・熟睡障害によって、必要な睡眠時間が十分に取れないことや睡眠の質の低下によって、日中の疲労、集中力の低下、心身の不調などが起こって、日常生活に支障をきたす状態です。
●過眠症
「過眠症」は、夜に十分な睡眠を取っているのに、日中に過剰な眠気がおきて、日常生活に支障をきたすような状態です。
●睡眠時随伴症
「睡眠時随伴症」は、睡眠中や睡眠から覚醒する際に、寝ぼけ行動や悪夢など不自然な行動や体験を伴う睡眠障害です。
うつ病
「うつ病」は、日本人の約15人に1人が一生のうちにかかるというありふれた病気です。憂うつな気分や意欲の低下などの精神症状や睡眠障害、頭痛、食欲不振などの身体症状が現れて、日常生活に支障をきたします。「うつ病」がどのような原因で発症するのかについては、まだわかっていませんが、特定の原因というよりさまざまな原因が複合的に影響して発症すると考えられています。
「うつ病」の精神症状には、集中力や決断力の低下もあげられ、これらが現れると物事を深く考えられなくなります。
病気に発展する要因
前章で紹介した通り、さまざまな病気が物事を深く考えられないことと関連しています。これらの病気に発展する要因としては、以下のようなものが考えられます。
睡眠不足
「睡眠」には、次の3つの役割があります。
・記憶の整理:脳の疲れをとり、記憶の整理をする。
・修復成長:傷ついた細胞を修復し、身体の成長を促す。
・疲労回復:身体の疲れをとり、病気の回復を促す。
睡眠不足や睡眠の乱れは、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの生活習慣病やうつ病、認知症など、さまざまな病気のリスクになると考えられています。
また、睡眠不足の時には、意欲の制御、集中力や注意力・判断力などに関わる脳の前頭葉がダメージを受けて、脳の活動が極端に低下しているという報告があります。
人間関係のストレス
職場の上司や同僚、家族や友人、恋人などとの人間関係のストレスは、うつ病や不安障害、適応障害、自律神経失調症など、さまざまな病気や心の不調を引き起こす可能性があります。これらの病気は、不眠、食欲不振、疲労感、集中力の低下、思考力の低下、決断力の低下、頭痛、動悸、めまい、不安、抑うつ症状などの症状を伴うことがあります。
人間関係のストレスは、自律神経のバランスを崩しやすく心身にさまざまな影響を及ぼすため、早めに対処することが重要です。
疲労の蓄積
疲労の蓄積は、自律神経失調症や生活習慣病などさまざまな病気の原因となります。特に常に身体がだるく、疲労感があり、日常生活に支障をきたす状態が長く続く場合には「慢性疲労症候群」の可能性があります。
慢性疲労症候群の主な症状には、以下のようなものがあります。
・強い倦怠感があり日常生活に支障が出ている。
・眠れない、寝た気がしない。
・物事を考えたり判断するのが難しいと感じる。
生活習慣の乱れ
生活習慣の乱れは、高血圧や糖尿病、脂質異常症、心筋梗塞、脳卒中など、さまざまな病気の原因となります。また、睡眠不足や、偏った食生活、運動不足、ストレスなど、生活習慣の乱れは脳の働きを低下させます。そのことにより集中力や判断力、記憶力などを低下させる原因となります。
症状を改善させて物事を考えられるようにするには
心身の不調が原因で物事を深く考えられない場合、次のような点を意識することで症状を改善できる可能性があります。
ストレス解消法を見つける
ストレスやストレスが原因の病気によって思考力が低下している時には、ストレスを解消する方法を見つけてみましょう。ストレス解消には、趣味や運動、相談などさまざまな方法があります。無理なく続けられる自分にあったストレス解消法を見つけることが大切です。
●趣味
音楽鑑賞、映画鑑賞、読書、料理など、好きなことをする時間を持つことでリラックスできます。
●運動
ウォーキングや軽いランニング、サイクリング、ダンス、ストレッチなどで、身体を動かすと気分転換になりストレスを解消できます。
●誰かと話す
信頼できる人に、悩みを相談することで気持ちが楽になることがあります。人に話すことで自分の考えが整理できたり、悩みを聞いてもらうだけでも心を落ち着かせる効果があります。
意識的に休息をとる
疲労が蓄積すると、さまざまな病気の原因となります。疲労がたまらないように意識的に休息をとるようにしましょう。疲労をためない休息のとり方のポイントを3つ紹介します。
●休みは先に決めておく
疲れがたまってからではなく、最初に休む日や休む時間を決めておきましょう。何もしない休日を作る、休憩時間はしっかりと休む、定時で帰る日を決めておくなどをすることで、疲労が軽減されます。
●疲労が蓄積していると時は連続で休む
疲労が蓄積している時は、有給休暇を足すなどして連続で休むようにしましょう。
●静かなストレス解消法を持つ
休みの日に、スポーツやアウトドア、飲み会などで気分転換すると、気持ちのリフレッシュにはなりますが体力を消耗します。疲れている時には積極的な休養が必要です。音楽鑑賞や読書、料理、散歩など身体をあまり使わない趣味を持つようにして、心と身体のリフレッシュを意識しましょう。
生活習慣の見直しと改善
生活習慣の見直しと改善は、健康維持や健康増進のために重要です。全国健康保健協会のホームページには、「生活習慣改善10カ条」が紹介されています。ぜひ参考にしてください。
●生活習慣改善10カ条
・その1【運動】適度な運動を毎日続けよう
・その2【たばこ】今すぐ、禁煙を!
・その3【食事(塩分)】塩分は控えめに
・その4【食事(脂質)】油っぽい食事は避ける
・その5【食事(肉類よりも魚のすすめ)】主菜は“肉より魚”を心がける
・その6【食事(野菜)】野菜をたっぷりとる
・その7【飲酒】お酒はほどほどに
・その8【歯の健康】毎食後歯を磨こう
・その9【ストレス】自分に合った方法でストレス解消
・その10【睡眠】規則正しい睡眠で十分な休養を
統合失調症が原因で物事を深く考えられない人の就活
先に説明した通り、物事を深く考えられないことと関連する病気の一つに「統合失調症」があります。統合失調症の方は、物事を深く考えられない以外にも、さまざまな症状で就職や転職が難しいケースがあります。
「atGP(アットジーピー)ジョブトレ」は、障害者の転職サービス業界 No.1の「atGP(アットジーピー)」が運営する就労移行支援サービスです。うつ病・発達障害・統合失調症・聴覚障害・難病といった障害別コース制で、障害に特化したサポートが受けられます。