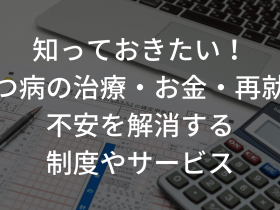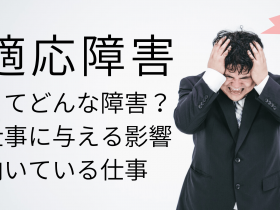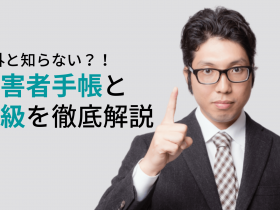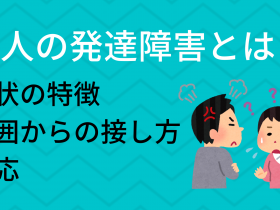就労移行支援と就労継続支援の違いとは?特徴や選び方のポイント
更新日:2024年02月19日
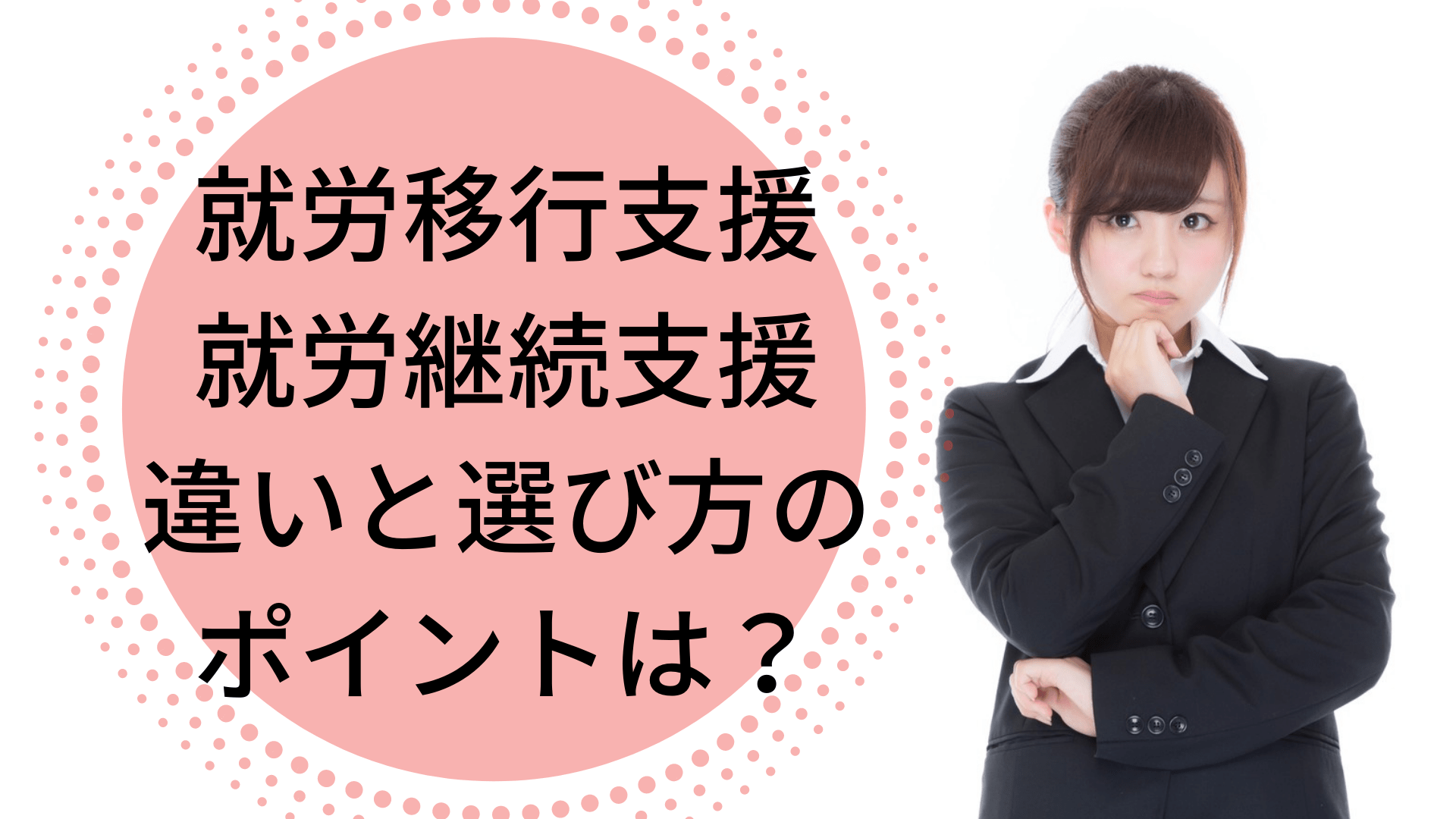
国連で採択された障害者権利条約や東京パラリンピックの招致などもあり、ノーマライゼーションの機運は高まっています。特に、障害者雇用に関しては、就労移行支援、就労継続支援といったサービスを利用し、一般就労を希望し実現する人が増加しています。ここでは、就労移行支援、就労継続支援とはどのようなサービスなのか、その違いや、利用条件、サービスの選び方のポイントなどについて解説していきます。 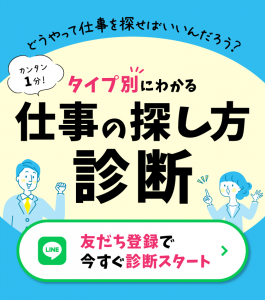
目次
就労移行支援とは

就労移行支援は障害者総合支援法におけるサービスの一つで、訓練等給付に分類されています。就労移行支援サービスの概要等は以下のとおりです。
概要
通常の事業所(一般企業)に雇用されることが可能と見込まれる者に対して、以下の訓練、支援をおこないます。
| ①生産活動、職場体験等の活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練 ②求職活動に関する支援 ③その適性に応じた職場の開拓 ④就職後における職場への定着のために必要な相談等の支援を行う |
期間
原則2年以内
ただし、必要があると認められる場合は最大で1年の延長可能
対象者
企業等への就労を希望する者(65歳未満)
ただし、65歳以上でも、継続して5年以上障害福祉サービスの支給決定を受けていて、65歳未満の時に就労移行支援の支給決定を受けた者は継続して利用可能
条件
本人のサービス利用希望があること
介護に関連するサービスでないため、障害支援区分の認定は必要ありません。
手帳が必要なのは身体障害者のみとなります
具体的な内容については関連記事もご参照ください。
就労継続支援とは

就労継続支援も就労移行支援と同様に障害者総合支援法の訓練等給付に位置づけられているサービスです。就労継続支援にはA型とB型があり、それぞれ以下のような特徴があります。
就労継続支援A型
概要
通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能な者に対して、雇用契約の締結等により就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービスです。
期間
制限なし
”一般の事業所に雇用されることが困難”なことが前提にあるので、継続的且つ、福祉的な支援を要するために期間については制限が設けられていません。
対象者
①移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者
②特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者
③就労経験のある者で現に雇用関係の状態にない者
こちらの事業についても原則65歳未満が対象ですが、満65歳以前に同事業の支給決定を受けた場合は継続して利用可能です。
条件
対象者のいずれかであり、サービス利用希望があることで、障害支援区分認定は不要
就労継続支援B型
概要
通常の事業所に雇用されることが困難であって,雇用契約に基づく就労が困難である者に対して行う、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うサービスです。
期間
制限なし
※理由はA型と同様、”一般の事業所に雇用されることが困難”なことが前提にあるので、継続的且つ、福祉的な支援を要するために期間については制限が設けられていません。
対象者
① 就労経験がある者であって、年齢や体力面で一般企業に雇用されることが困難となった者
② 50歳に達している者又は障害者基礎年金1級受給者
③ ①、②に該当しない者で、就労移行支援事業者等によるアセスメントにより、就労面に係る課題等の把握が行われている者
条件
上記の対象者のいずれかであり、サービス利用希望があることで、障害支援区分認定は不要
具体的な内容については関連記事をご参照ください。
就労移行支援と就労継続支援の違いとは

就労移行支援と就労継続支援の違いは、一般企業での雇用が見込まれるか否かにあります。
就労移行支援は通常の事業所、つまり一般企業等での雇用が可能と見込まれる障害者、一方、就労継続支援の方は、通常の事業所での雇用が困難な障害者とされています。
就労移行支援は一般企業で働く前準備
就労移行支援の対象者は一般の事業所で働くことを希望し、且つ、必要な支援を受ければ就労が可能と思われる障害者です。内容的にも就職に直結するようなスキル(面接や履歴書、コミュニケーション、パソコンなど)の習得であったり、就活や就労後のフォローであったり、職場体験などが多く含まれています。
また、生産活動も含まれていますが、労働自体が目的ではないので、就労支援では原則として工賃が発生しません。
「どうやって仕事を探せばいいんだろう・・」そんなあなたには簡単1分でタイプ別にわかる!仕事の探し方診断がおすすめです。
就労継続支援は一般就労が難しい場合のサービス
就労継続支援の対象者は、一般の事業所では現状就労が難しい障害者です。提供されるサービスも就労継続支援での就労のために必要な知識、能力の向上のための訓練が主となります。
実際の一日のサービスの内容は就労の機会の提供で、作業をすることがメインとなります。当然ですが、就労を提供するということは労働に応じた工賃が支払われます。
A型とB型の違いは、雇用契約があるかないかにあります。
A型は雇用契約に基づくため、工賃には最低賃金が保障されます。B型と比較すると月額工賃も平均78,950円(令和1年度実績)と高くなりますが、労働内容や仕事に求められる質や量は一般の企業に近いものになります。
B型の場合、雇用契約がないため、利用者のやる気や障害特性などに応じて主に軽作業を行うことが仕事の内容となります。工賃も月額約16,369円と、お小遣い程度にしかならず、世帯所得で1割の自己負担が発生する場合、利用料が工賃を上回るということもあり得ます。
当然、国はこの低工賃は課題であるとして増額に向けた取組みを実施しています。
就労移行支援と就労継続支援それぞれの進路
就労移行支援と就労継続支援の利用者が実際どれくらい一般就労に至っているのかは気になると思いますので、近年の厚生労働省の統計から簡単にまとめてみましょう。

就労移行支援の利用者は約半数が一般就労に移行しています。
就労継続支援A型では約1/4、就労継続支援B型では13%程度です。
それぞれのサービスの利用者の総数に違いがあることから、就労継続支援A型、B型では一般就労に移行する機会が少ないことがわかります。
通所する期間に制限がないこともあり、実際に長年に渡って利用する人も多いのが就労継続支援サービスです。一般就労に移行できない人の居場所にもなっているといえるでしょう。
このデータはあくまで全体の平均です。事業所によって割合は変わってくることに留意しましょう。
就労移行支援と就労継続支援の選び方
就労移行支援と就労継続支援の違いや特徴などに基づいて、サービスをどのように選べばよいか解説します。
いずれ一般企業で働きたい場合は就労移行支援事業所
就労移行支援はその対象者を一般の事業所で働くことが可能と見込まれる者としています。
そのため、このサービスの利用に適している人は以下の様な人です。
・一般の事業所での就労を希望している
・障害や病状が安定していて、ある程度長期に働ける
・安定した収入を得たい
就労移行支援はあくまで一般の事業所で働きたい人のためのサポートのためのサービスです。
収入を得たり、長期利用はできないことに留意する必要があります。無論、2年間利用する必要はなく、利用期間中に就職が決まればすぐに一般の事業所での就労に移行することもできます。
一般企業で働く希望のない場合は就労継続支援
就労継続支援について、対象者は移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった者、特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった者、就労経験のある者で現に雇用関係の状態にない者となっています。
具体的には以下の様な人に向いています。
・働くためのスキルが未熟
・障害により安定して働けない
・精神的に不安がある
・一般の事業所での就労よりも配慮を受けて安心して働きたい
一般の事業所で就労するには自身の適性や障害を理解し、安定して働けることが求められます。焦らず、規則的に働くことや、必要なスキルをまず就労継続支援サービスで経験、習得し、確実にステップアップしましょう。
一般の事業所での就労にこだわらないという人は、就労継続支援サービスは仲間や支援員に囲まれた楽しい場所となるでしょう。
まとめ
障害者の就労には国の手厚い支援があります。
就労移行支援は一般の事業所でのもう少しのスキルアップや適性の見極めで就労可能な人への支援です。
就労継続支援は現状では一般の事業所での就労が様々な理由で難しいと考えられる人への支援です。
ご自身の適性や障害の現状、働きたい度合い、得たい収入など、総合的に考えてどのサービスを利用するべきかよく考えて選択しましょう。
就労移行支援事業所atGP(アットジーピー)ジョブトレとは?
ゼネラルパートナーズ(以下GP)は障害者の転職・就職を総合的にサポートしています。GPでは、就労系福祉サービスのなかでも一般就労へ大きなチャンスがある就労移行支援事業所atGPジョブトレを運営しています。
数字が示すジョブトレの強み
・事務職での就職率 94.5%
・就職後の定着率 91.4%
2019年度実績ですが、事務職での採用は94.5%と、かなりの高い率となっておりatGPジョブトレが事務職に強いことがわかります。
また、障害者採用での課題である定着率は91.4%で、atGPジョブトレによる企業とのマッチングが適切であることと、就職後のフォローが充実していることが理解していただけます。
atGPジョブトレの利用者は幅広い業界で活躍しています
atGPジョブトレの就職先の業界は多岐にわたっています。
・サービス
・人材
・金融
・官公庁・公社・団体
・ソフトウェア・通信
・メーカー
・鉄道・航空・運輸
・医療・福祉・教育
・その他(商社・不動産・マスコミなど)
(2019年9月~2020年8月の就職データ)
atGPジョブトレの4つの特徴
ポイント1:障害別のコース制(うつ病、発達障害、統合失調症、聴覚障害、難病)
・障害別のプログラムで一人ひとりに合った対策をおこないます
・同じ障害と向き合う仲間とともにトレーニング!あなたの居場所がここにあります
ポイント2:事務職で活躍できるスキルが身につく
・事務職での就職を目指したスキルを習得できます
・カリキュラムの6割が職場で力を発揮できるようになるための実践的なトレーニングとなっています
ポイント3:「就職後」を意識した就職活動サポート
・初めての障害者採用でも安心の手厚いサポートをします
・福祉はもちろんさまざまな業界出身のスタッフが即戦力になるための実践的なアドバイスをします
ポイント4:一人ひとりと向き合う満足度の高い支援
・専任のスタッフが個別面談をとおして障害理解と対処法を一緒に考えます
・最適な対処法を見つけるためスタッフ全員がチームとなってサポートします
ジョブトレの6つのサポート方針
1.ありのままの自分をさらけ出しても、安心して過ごすことができる
2.失敗大歓迎。自分にあったやり方を自ら見つける実験の場として利用できる
3.自分の人生を自らの意思や行動によって、自分の足で主体的に歩むことができる
4.利用者様同士の情報や気持ちの交換によるピアサポートが互いを支えあう力になる
5.一人ひとり違うという個別性が重視され、自分にあった支援を受けることができる
6.未来について自己決定が尊重され、選択の自由を奪われない
ジョブトレの詳しいサービス内容はリンクをご覧ください
→ 障害別コース制の就労移行支援サービス|atGPジョブトレ